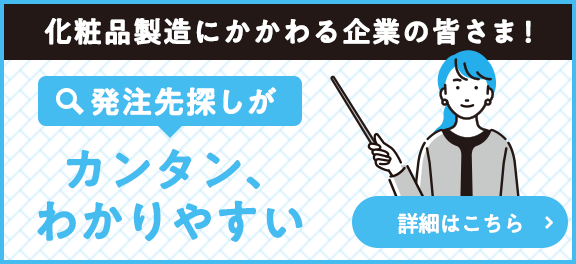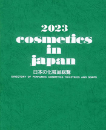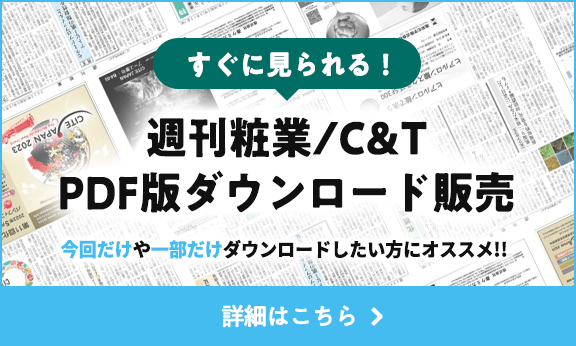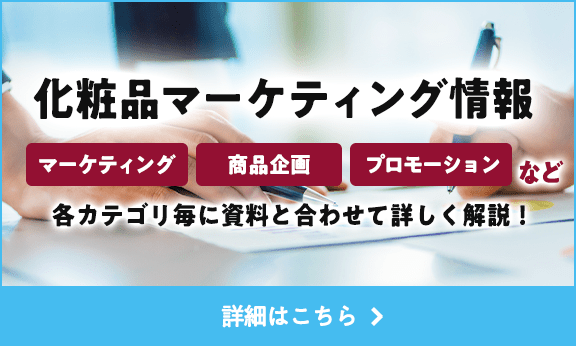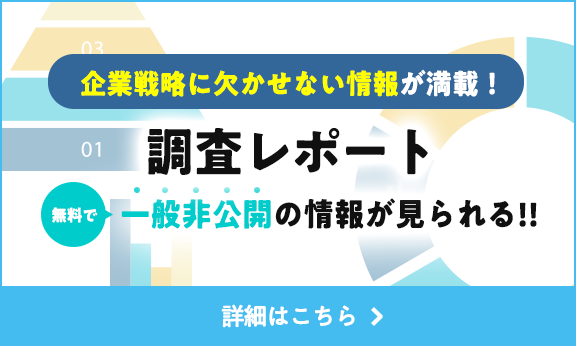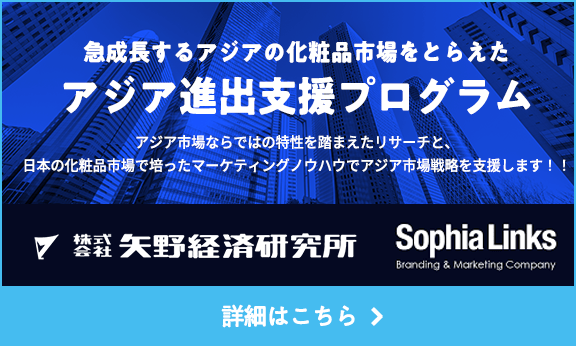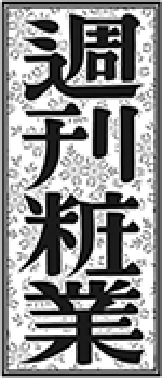第1回 ラベルではなくレベル
はじめに
化粧品の知識は、有象無象の情報を読み解く力が必要である。例えばよく「コラーゲンは肌にいい」といわれる。しかし、コラーゲンを多く含む食品を食べたとしても、体内でいったん消化してから吸収されるわけである。消化されたものが、荒れた肌にちょうどいい分量だけ行き渡るかどうかなどわからない。情報の信憑性を見極めるのがリテラシー(読み解く力)である。今回、本誌の加藤英俊編集長のご好意によりこの紙面をお借りして、読者諸氏に化粧品の技術面からリテラシーを養う一助となればとの思いからできるだけ平易に記してみようと考えている。
まず日本の化粧品の技術者は、客観的にどの程度のレベルなのだろうか?どんな研究をしているのだろうか?ということについて紹介する。
化粧品の技術者集団
今、日本の化粧品研究者は、日本化粧品技術者会に個人会員として約1500名が登録している。実際の数はその数10倍になると思う。この母体組織である国際化粧品技術者連盟(The International Federation of Societies of Cosmetic Chemists、以下IFSCCと略す)は1959年に設立され、50年の歴史をもつ世界各国の化粧品技術者会の連合組織である。
当初は、ベルギーのブリュッセルで、イギリス、アメリカ、フランス、西ドイツ、オランダの技術者により発足した。翌1960年、ミュンヘンで第1回総会が開かれた。日本からオブザーバーとして資生堂取締役の小山常正氏が出席し、アメリカの推薦により満場一致で加盟が承認された。その推薦には、ニューヨークのエバンズ・ケメテック社(戦前に資生堂が技術提携したゾートス社の後身)のロバート・A・クレーマーの助力があった。当初総会は2年ごとに、ロンドン・ニューヨーク・パリと開かれ、第5回が1968年5月12日から1週間、16カ国が参集して東京で開催された。この時小山氏はIFSCC会長に選ばれた。任期は1年である。この日本開催が世界に化粧品技術の扉を開くスタートになった。
現在、IFSCCは本部事務局をロンドンに置き、化粧品技術の向上、ひいては安全で有用な化粧品開発のための諸活動を国際規模で行っている。IFSCCに加盟している化粧品技術者会は45カ国、総会員数は1万5000名弱。この行事のうち、最大なものは各国の化粧品技術者が一堂に介して、研究成果を発表し、討論することを目的として開催される学術大会である。
この学術大会は西暦偶数年に開催される本大会(Congress)と西暦奇数年に開催される中間大会(Conference)に分けられる。これらの開催地頻度は、ヨーロッパ地域が2、北南米地域が1、アジアなどのその他の地域が1の割合のサイクルでオリンピックのように世界中で行われる。さらに開催国の技術者会が、経済的資金面や応募された論文を審査することの能力を求められるため国も限定されている。アメリカ、フランス、日本、ドイツ、イギリス、韓国、ブラジル、スペイン、イタリア、アルゼンチン、オランダで本大会を開催し、加えてオーストラリア、台湾、ベルギー、南アフリカ、タイ、トルコ、メキシコ、スカンジナビアまでの20カ国が中間大会を開催する機会が与えられている。ちなみに来年はブエノスアイレス大会である。
そこは世界各国の化粧品技術者が多数集まり、化粧品科学技術の最も権威ある研究発表会で、特に日本からの研究発表は、その学問的価値、化粧品としての応用可能性が極めて高いとして、常に世界の注目をあびている。本大会に化粧品研究に関連して最も優れた発表を行った研究者に与えられるIFSCC最優秀賞、優秀賞を資生堂、ポーラ、花王、コーセー、日光ケミカルズなどがほぼ毎回のように受賞している。日本の技術レベルは世界一である。
その他にアジア化粧品技術者会研究発表会(Scientific Conference of Asian Societies of Cosmetic Scientists:ASCS)がある。アジア地区における化粧品技術の向上と化粧品産業の一層の発展を図り、アジアの化粧品技術者相互の交流を深めることを目的として日本が提案・参加を呼びかけ、2009年3月には第9回ASCS大会が横浜市のパシフィコ横浜で開催された。
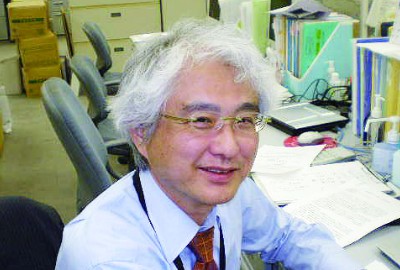
島田邦男
琉球ボーテ(株) 代表取締役
1955年東京生まれ 工学博士 大分大学大学院工学研究科卒業、化粧品会社勤務を経て日油㈱を2014年退職。 日本化粧品技術者会東京支部常議員、日本油化学会関東支部副支部長、日中化粧品国際交流協会専門家委員、東京農業大学客員教授。 日油筑波研究所でグループリーダーとしてリン脂質ポリマーの評価研究を実施。 日本油化学会エディター賞受賞。経済産業省 特許出願技術動向調査委員を歴任。 主な著書に 「Nanotechnology for Producing Novel Cosmetics in Japan」((株)シーエムシー出版) 「Formulas,Ingredients and Production of Cosmetics」(Springer-Veriag GmbH) 他多数
ライブラリ・無料
ダウンロードコーナー

PDF版 ダウンロード販売
気になる刊行物をPDFで
ダウンロード
紙面を探す

化粧品
マーケティング情報
マーケティングに役立つ
情報が満載
紙面を探す

調査レポート
化粧品業界での戦略に
役立つレポート
レポートを探す

粧界データ集
メーカー製品一覧などの
データ集をダウンロード
無料でダウンロード

化粧品容器カタログ
ライブラリー
容器メーカーの
最新カタログを公開中
カタログを探す

デジタル紙面版
2010年1月から最新号まで
デジタルアーカイブ化
無料で見る
刊行物紹介

週刊/毎週月曜日発行
週刊粧業
化粧品、日用品、医薬品、美容業、装粧品、エステティック等を中心とした生産・流通産業界の総合専門情報紙。

季刊/年4回
C&T
化粧品、日用品、アクセサリーなどの業界別の市場動向をはじめ、戦略、流通、経営、マーケティングを扱う情報専門誌。
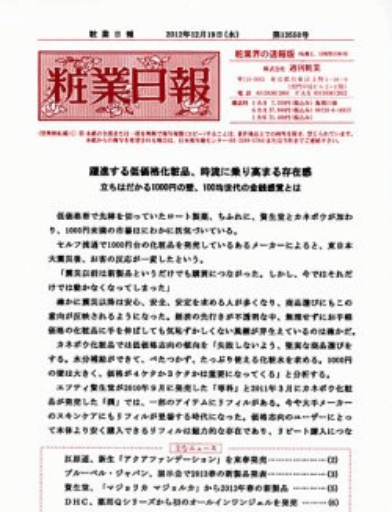
週刊/毎週月曜日発行
粧業日報
化粧品、トイレタリー、石鹸、歯磨、日用品に関する情報の速報版。業界のエグゼクティブ必読の情報紙。
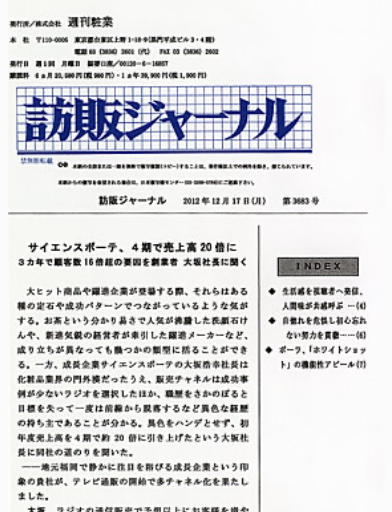
週刊/毎週月曜日発行
訪販ジャーナル
昭和33年に創刊された、わが国初の訪問販売化粧品業界の専門情報紙。
速報ニュース
アクセスランキング
- 日間
- 週間
- 月間