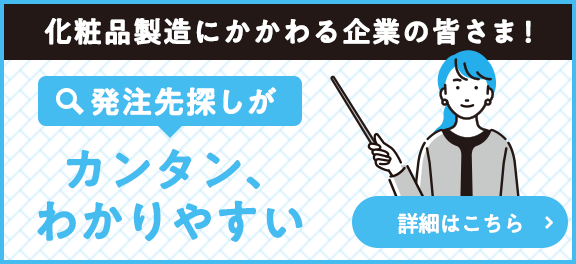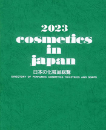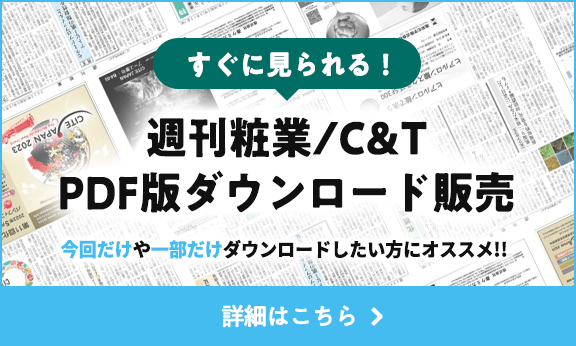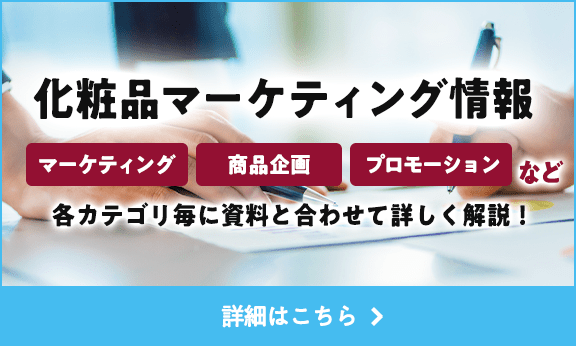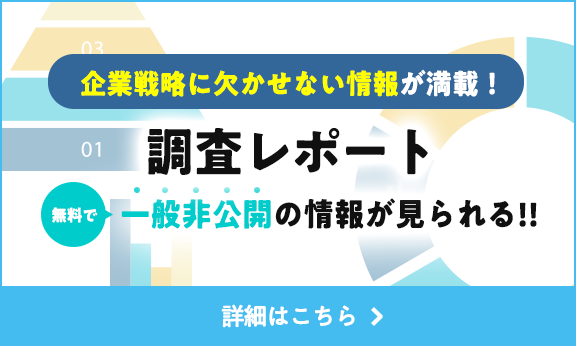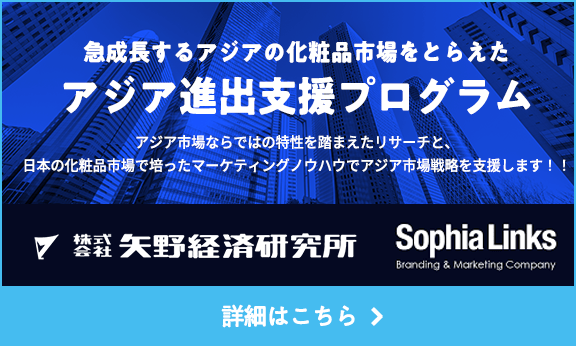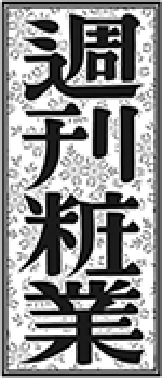第4回 GNPではなくGMP
はじめに
私が2010年の2月に米国出張していた時に、日本以上にテレビのニュースは「TOYOTA」「RECALL」の話題一色だった。
発端はブレーキの不具合で家族3人が死亡したという事故へのトヨタの対応だった。2月4日の記者会見で品質保証担当重役は、「ブレーキが利かなくなったことには違和感を持つ可能性がある」と認めながら車両欠陥の認識はないことを強調し、顧客目線から外れたトヨタの信頼感は大きく揺らいだ。10日にリコール発表しても、後手となり一気に逆風で、2月24日のアメリカ合衆国代議院監視・政府改革委員会の米公聴会で豊田章男社長は「深く謝罪」した(図1)。
しかし創業者豊田佐吉の曾孫であることから、トヨタのテレビCMを捩って「こども社長」と揶揄され、公聴会で話した英語を「米国の大学でMBAを取得したレベルと思えないほど幼稚」と叩かれた。就任以来一度も単独インタビューに応じたことがなく、こうしたトヨタの対応は「製品品質ではなく経営者の質の問題」「世界標準を満たしていない」と問題視までされてしまった。
誰でも品質が大事という。そこで化粧品工業連合会から発表されている自主基準について考えてみる。
化粧品のGMP1)
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用器具に関する規則を定めた法律の親玉である薬事法に化粧品がどのように規定されているかを見てみよう。化粧品の製造販売および製造に関しては第四章の第12条および第13条に次のようになっている。
●第12条(化粧品製造販売業の許可)
製造販売業許可を受けた者でなければ化粧品の製造販売をしてはならない。
●第12条二(化粧品製造販売業許可の基準)
化粧品の品質管理の方法がGQP省令に適合しないとき、及び製造販売後安全管理の方法がGVP省令に適合しないときは製造販売業許可を与えない。
●第13条(化粧品製造業の許可)
製造業許可を受けた者でなければ化粧品の製造をしてはならない。製造所の構造設備が薬局等構造設備規則(省令)で定める基準に適合しないときは化粧品の製造許可を与えない。
GQP省令とは品質管理の基準に関する省令で、GVP省令とは製造販売後の安全管理の基準に関する省令のことである。以上のように薬事法では、化粧品製造時に遵守を義務づけているのは製造所の構造設備に関する規則のみで、医薬品に見られる「製造および品質に関するGMP」の遵守を義務づけていない。
標題の一つGMPとはGood Manufacturing Practiceの略で、化粧品の製造管理及び品質管理に関する基準である。ゆえに、化粧品GMPは「化粧品の製造管理及び品質管理に関する基準」で従業員、設備、製造、製品、原材料等の取扱いや実施方法を定めたものである。勉強せずに化粧品製造を行ったり化粧品製造を指図したりするのは、道路交通法を勉強せずに自動車運転するようなものである。
しかし驚かれるかもしれないが、化粧品のGMPは1981年以前に規定をされていなかった。2008年になって、2007年11月に発表されたISO22716『Cosmetic-GMP-Guideline on Good Manufacturing Practices, ISO/FDIS 22716』を日本化粧品工業会が業界自主基準として採用することになった。業界自主基準とは業界規格で業界の掟である。医薬品と違い法令要件ではないので、罰則規定はない。ただし、化粧品会社は法令並の重さをもって遵守する必要がある。
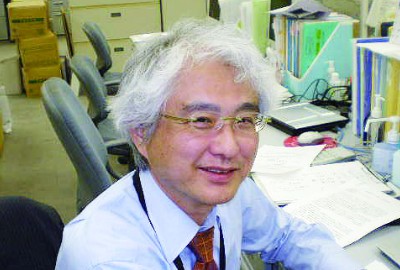
島田邦男
琉球ボーテ(株) 代表取締役
1955年東京生まれ 工学博士 大分大学大学院工学研究科卒業、化粧品会社勤務を経て日油㈱を2014年退職。 日本化粧品技術者会東京支部常議員、日本油化学会関東支部副支部長、日中化粧品国際交流協会専門家委員、東京農業大学客員教授。 日油筑波研究所でグループリーダーとしてリン脂質ポリマーの評価研究を実施。 日本油化学会エディター賞受賞。経済産業省 特許出願技術動向調査委員を歴任。 主な著書に 「Nanotechnology for Producing Novel Cosmetics in Japan」((株)シーエムシー出版) 「Formulas,Ingredients and Production of Cosmetics」(Springer-Veriag GmbH) 他多数
ライブラリ・無料
ダウンロードコーナー

PDF版 ダウンロード販売
気になる刊行物をPDFで
ダウンロード
紙面を探す

化粧品
マーケティング情報
マーケティングに役立つ
情報が満載
紙面を探す

調査レポート
化粧品業界での戦略に
役立つレポート
レポートを探す

粧界データ集
メーカー製品一覧などの
データ集をダウンロード
無料でダウンロード

化粧品容器カタログ
ライブラリー
容器メーカーの
最新カタログを公開中
カタログを探す

デジタル紙面版
2010年1月から最新号まで
デジタルアーカイブ化
無料で見る
刊行物紹介

週刊/毎週月曜日発行
週刊粧業
化粧品、日用品、医薬品、美容業、装粧品、エステティック等を中心とした生産・流通産業界の総合専門情報紙。

季刊/年4回
C&T
化粧品、日用品、アクセサリーなどの業界別の市場動向をはじめ、戦略、流通、経営、マーケティングを扱う情報専門誌。
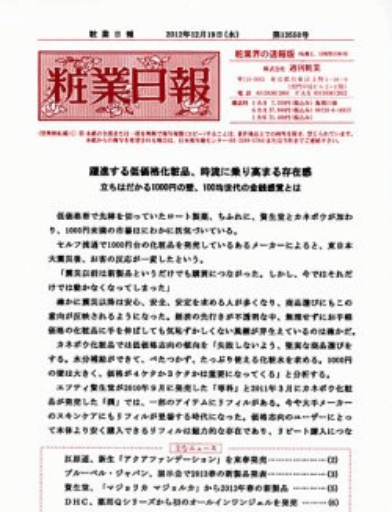
週刊/毎週月曜日発行
粧業日報
化粧品、トイレタリー、石鹸、歯磨、日用品に関する情報の速報版。業界のエグゼクティブ必読の情報紙。
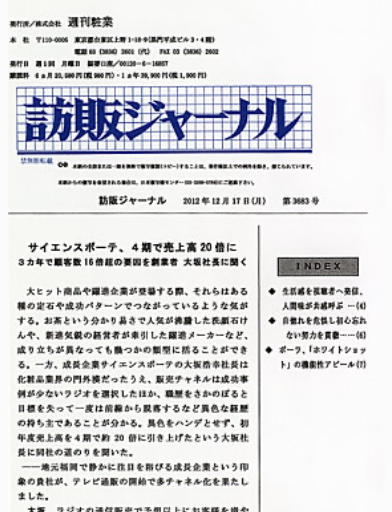
週刊/毎週月曜日発行
訪販ジャーナル
昭和33年に創刊された、わが国初の訪問販売化粧品業界の専門情報紙。
速報ニュース
アクセスランキング
- 日間
- 週間
- 月間