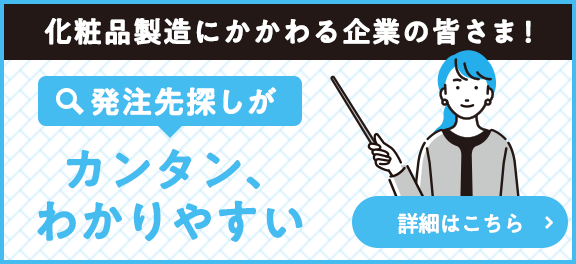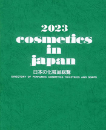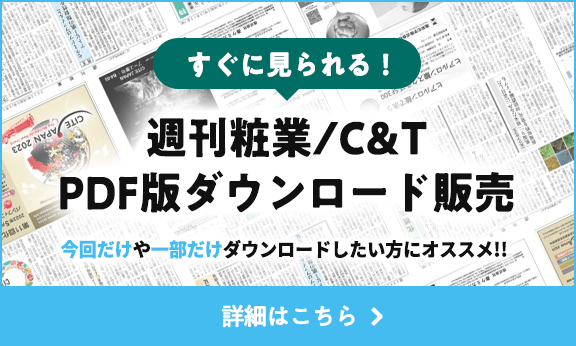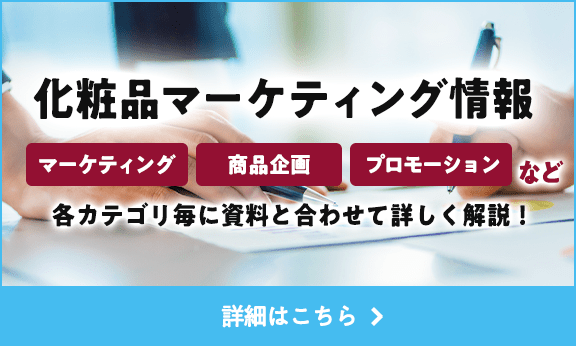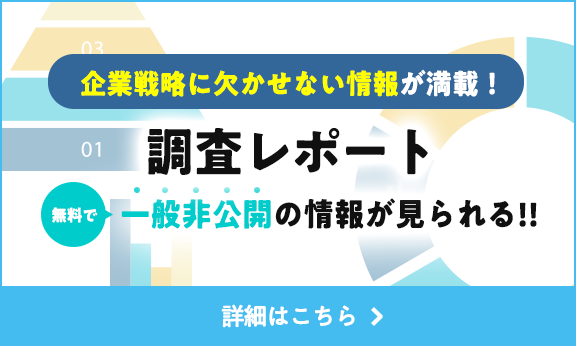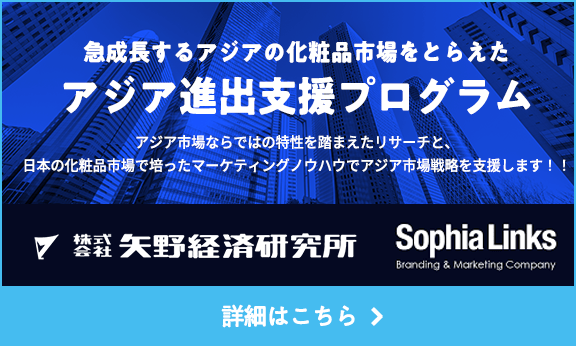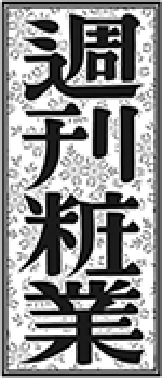第25回 見ずではなく水
【C&T2016年1月号8面にて掲載】
はじめに
約71%を水で覆われている地球は、宇宙の「ハビタブルゾーン」である。地球以外の惑星や衛星は、液体の水で存在する例は少なく氷や水蒸気である。液体の水が存在できる温度範囲は高圧ほど広くなる。
NASA(米航空宇宙局)は、火星に今も液体の水が存在していることを裏付ける観測結果を発表したが、火星のような気圧の低い環境では、液体の水は安定的に存在することはできない。同じくNASAでは、冥王星に青空、地表の下には氷の岩盤がある可能性が高いと発表した。水は海から蒸発し、雨や雪となって地表をうるおすので無限と考えられているが、液体の淡水は1%以下である。貴重な有限資源だ。
化粧品でもっとも多く配合されている原料は水である。今のところ、液体の水を配合しなければいけない化粧品を使えるのは宇宙で地球だけ? とも言える。今回は性状が「無色透明な液でにおい及び味がない」、見ずじまいで気にすることのない水を改めて考えてみる。
化粧品原料の水
主に化粧品原料として使用する水は常水と精製水の2種類になる。ヘアケア製品等の一部に使用される例がある常水は、水道法第4条に基づく水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)の純度試験(アンモニウムを0.05mg/L以下)に適合しており、水道水である。
しかし、水道水は塩素で殺菌されているため、残留塩素や塩化物、金属塩などが存在し、本来は化粧品原料の水には適さない場合が多い。また塩の存在が化粧品の安定性に影響することもあり、一般的には不純物の少ない精製水が使用される。
水道水からの精製水製造過程ではイオン交換樹脂による脱塩が行われる。この場合はフィルターろ過や紫外線照射などによる殺菌対策をしている。水は電気をよく通すと言われるが、ちなみに純粋な水は電気を通しにくくなる。表1に、スキンケア製品とメークアップ製品に使用する水の目的をそれぞれの化粧品の種類や剤型ごとにまとめる。
(表1 化粧品分類と水の配合目的)
化粧品の中の2つの水
製品中の水などのうち、一定の位置に固定されていて、ほかの物質と何らかの結合状態(水和の状態を含む)にあって運動が著しく制限されている結合水がある。
一方、製品中の水で、結合水以外の状態をとっている水を自由水と定義している。運動に制限のない自由に移動できる水で、液体の水と同様の挙動を示す。エタノールなどを含む化粧水が0℃付近でも凍結しないのは、結合水が多いからである。
皮膚の水
皮膚の最外層には、角層細胞が15~20層に積み重なった、厚さ20μm程度の角層があり、皮膚を乾燥から守るバリア機能の役割を果たしている。角層の水分量は、10~20%の時に自然な柔軟性を示し、10%以下になるとひび荒れ、肌荒れが生じると言われている。
角層の水分は、角層内のイオン類、アミノ酸、タンパク質などの分子に結合して運動が制限されているもので、一次結合水と二次結合水に分けて考えられている。一次結合水は、160℃で3分加熱してはじめて結合が外れる水であり、通常角層に5%以上含まれている。
一方乾燥した状態でゆっくり離れていくような比較的弱い結合をする水を二次結合水と呼ぶ。この水は、温度、湿度などの外部環境により比較的容易に吸着、脱離を繰り返しうる水で、角層の水分保持はこの二次結合水をいかに保ちうるかにかかっている。
二次結合水の量は共存するタンパク質の分子量や形態、天然保湿因子の種類や量、および脂質の種類や量によっても異なる。二次結合水の容量を超えて角層が水を含んだ場合は、ほとんどが運動に制限のない自由水であり、一定量を超えると過水和になる。この時に角層細胞は柔らかくて強靭であった性質を失い、張りがなく脆いものとなり、最終的に破壊される。
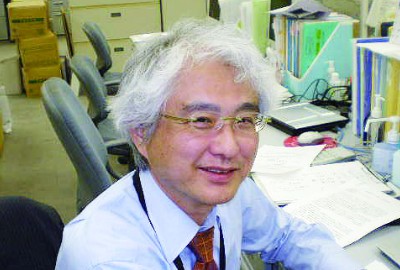
島田邦男
琉球ボーテ(株) 代表取締役
1955年東京生まれ 工学博士 大分大学大学院工学研究科卒業、化粧品会社勤務を経て日油㈱を2014年退職。 日本化粧品技術者会東京支部常議員、日本油化学会関東支部副支部長、日中化粧品国際交流協会専門家委員、東京農業大学客員教授。 日油筑波研究所でグループリーダーとしてリン脂質ポリマーの評価研究を実施。 日本油化学会エディター賞受賞。経済産業省 特許出願技術動向調査委員を歴任。 主な著書に 「Nanotechnology for Producing Novel Cosmetics in Japan」((株)シーエムシー出版) 「Formulas,Ingredients and Production of Cosmetics」(Springer-Veriag GmbH) 他多数
ライブラリ・無料
ダウンロードコーナー

PDF版 ダウンロード販売
気になる刊行物をPDFで
ダウンロード
紙面を探す

化粧品
マーケティング情報
マーケティングに役立つ
情報が満載
紙面を探す

調査レポート
化粧品業界での戦略に
役立つレポート
レポートを探す

粧界データ集
メーカー製品一覧などの
データ集をダウンロード
無料でダウンロード

化粧品容器カタログ
ライブラリー
容器メーカーの
最新カタログを公開中
カタログを探す

デジタル紙面版
2010年1月から最新号まで
デジタルアーカイブ化
無料で見る
刊行物紹介

週刊/毎週月曜日発行
週刊粧業
化粧品、日用品、医薬品、美容業、装粧品、エステティック等を中心とした生産・流通産業界の総合専門情報紙。

季刊/年4回
C&T
化粧品、日用品、アクセサリーなどの業界別の市場動向をはじめ、戦略、流通、経営、マーケティングを扱う情報専門誌。
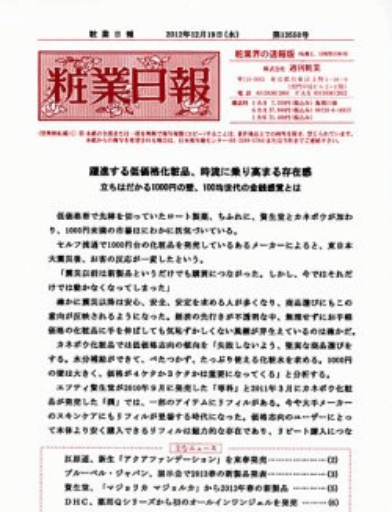
週刊/毎週月曜日発行
粧業日報
化粧品、トイレタリー、石鹸、歯磨、日用品に関する情報の速報版。業界のエグゼクティブ必読の情報紙。
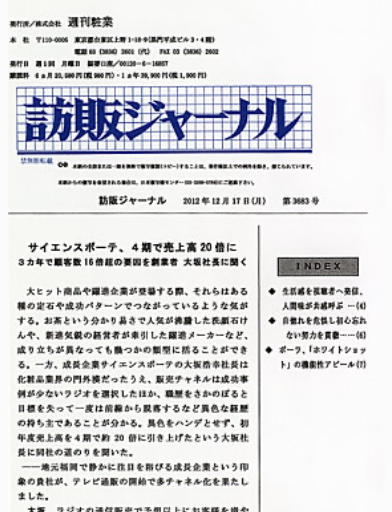
週刊/毎週月曜日発行
訪販ジャーナル
昭和33年に創刊された、わが国初の訪問販売化粧品業界の専門情報紙。
速報ニュース
アクセスランキング
- 日間
- 週間
- 月間