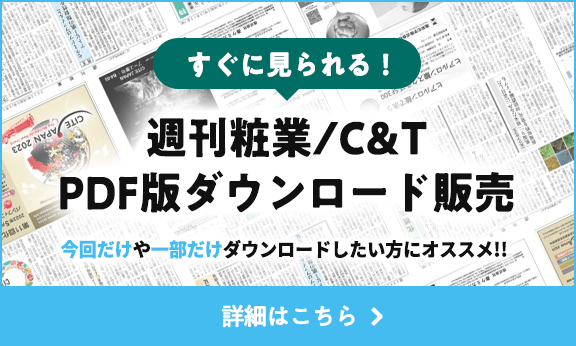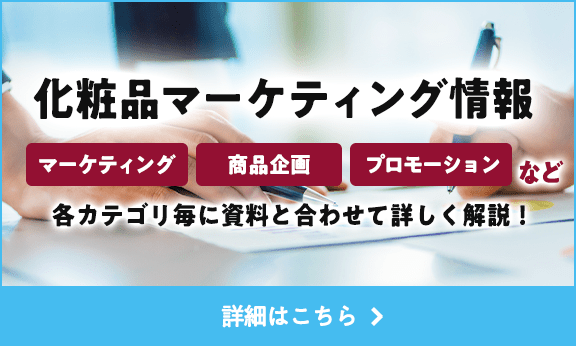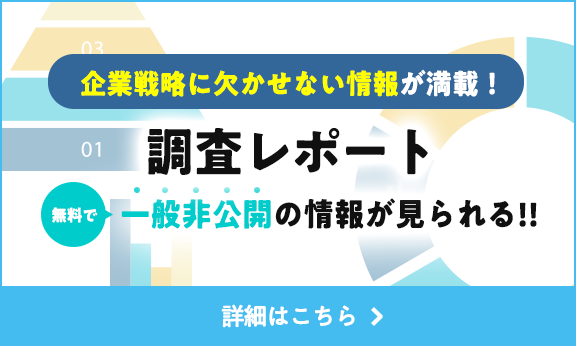第40回 『やめられない』ではなく『止める』
【C&T2019年10月号7面にて掲載】
はじめに
私たちの体には、ウイルスや細菌などの異物が入ってきたときに体内で「抗体」がつくられ、これらの外敵をやっつけようとする「免疫」という仕組みが備わっている。
ところが、この免疫の仕組みが食べ物や花粉など私たちの体に害を与えない物質に対しても「有害な物質だ!」と過剰に反応し、攻撃をし過ぎる結果、逆にマイナスの症状を引き起こしてしまうのが「アレルギー」だ。本来は体を守るはずの反応が、自分自身を傷つけてしまうアレルギー反応に変わる。
かゆみを伴う湿疹が、良くなったり悪くなったりを繰り返す「アトピー性皮膚炎」もその一つ(図1)。厚生労働省の調査によると、わが国における患者数 は、2014年時点で45万6000人にものぼる。その対策を訴求しているスキンケア製品も多い。
今回は、成人で1割弱もみられる疾患であり、当事者にとって深刻な痒みの『やめられない』アトピーについて述べる。
図1 痒みの止まらないアトピー患者
アトピーの発症
アトピーという名称は、「特定されていない」「奇妙な」という意味のギリシャ語「アトポス」(atopos-a=否定、topos=由来)に由来する。この病気は、「バリア機能が弱い」という皮膚の素質と「アレルギー体質」という2つの遺伝的な体質に、環境の因子が刺激を与えて起きると考えられている。
アレルギーの原因となる物質を「アレルゲン」または「抗原」といい、アレルゲンが体内に入ってくると、これをやっつけようと「IgE(アイジーイー)抗体」というタンパク質がつくりだされる。このIgE抗体は、皮膚や粘膜に多くあるマスト細胞の表面に、まるでアンテナのように張りめぐらされている。
再びアレルゲンが侵入し、このIgE抗体のアンテナにひっかかり結合したとき、マスト細胞の中につまっているヒスタミンなどの化学物質が一気に放出され、かゆみなどの症状があらわれてくる(図2)。
図2 アレルギー反応がおこる仕組み
もう少し詳しく話すと、「インターロイキン4」や「インターロイキン13」といったサイトカイン(細胞の出すタンパク質)を出すTh2リンパ球(白血球の一種)が活発に働き過ぎてしまう。Th2リンパ球が活発に暴れて炎症が起きると、「インターロイキン4」や「インターロイキン13」が大量に出て、IgE抗体を作らせるという仕組みだ。皮膚のバリア機能が弱いと、皮膚の乾燥や外からの刺激に対して炎症を起こしやすくなる。
皮膚科医診断では、症状が乳児では2カ月以上、その他の場合は6カ月以上の慢性であるかどうか、かつ反復して起こっているかを確認し、「接触皮膚炎」やヒゼンダニの寄生によって生じる「疥癬(かいせん)」、「皮膚リンパ腫」や「乾癬(かんせん)」などアトピー性皮膚炎とは異なる皮膚疾患との鑑別をする。
アトピー対策
対策は、①スキンケア②薬物療法③悪化因子の3本柱が基本になる。まずスキンケアについては、角質層の中の水分量が低下しているので、乾燥肌(ドライスキン)になっている。皮膚を清潔に保つことは大切だが、皮膚を傷つけることがないよう、あまりゴシゴシ洗わないようにする。
また、石けんや洗浄剤の過度の使用は、かえって乾燥を悪化させることがあるので、使い過ぎには気を付ける。よく泡立てて、刺激が少ない方法で皮膚の汚れを落とすとよい。
シャワー浴よりも入浴の方がよく、湯温は、おおむね38度から40度と、ぬるめの湯にゆっくり浸かるのがよい。また、正常に見える部分も含め、全体に保湿外用剤を使用する。入浴直後の使用が効果的だとされている。
次に、皮膚に直接使用できる外用薬の塗布が基本で、その際「何を」「どこに」「どれだけ」そして「いつまで」塗るかを意識した使い方が大切だ。炎症を抑えるために最も重要な薬剤はステロイド外用薬で、一般的にストロンゲスト、ベリーストロング、ストロング、ミディアム、ウイークの5段階にランク分けされており、それを指標として重症度に見合ったランクの薬剤を使用する。
ランクや使用量は、症状に応じて異なるが、ステロイドの副作用に対する忌避感で勝手に減量したりすると、治療に対する十分な効果は得られない。長期間のステロイドの使用は、皮膚が薄くなったり内出血をしたりといった副作用があるので、症状が治まってきたら徐々にステロイド外用薬の使用間隔を空けたりする。
最後に、ダニや花粉、ペットの毛などの環境アレルゲンが悪化因子であれば除去する。また、バランスの良い食生活を心掛け、特定の食物による悪化が確認されていない限りは特別な制限は必要ない。規則正しい生活で、十分な睡眠時間を確保する。
適度な運動による発汗は、皮膚の保湿に良いとされているが、かいた汗は放置せずにシャワー浴やお湯を絞ったタオルで拭く。加えて、風邪をひいたり、とびひやヘルペスなどの感染症、ストレスもアトピー性皮膚炎の悪化に関係しているといわれており、持続的なストレスがあるときには対策を検討する。
2018年4月には、バイオ製剤である「デュピルマブ」が発売された。これは、「インターロイキン4」や「インターロイキン13」の働きをブロックする抗体製剤で、これまでの治療で症状がコントロールできなかった重症例で使われ、大きな効果を発揮している。また、再燃を繰り返す湿疹に対しては、図3に示す「プロアクティブ療法」が行われている。
これは、症状が出た時だけに外用する「リアクティブ療法」に対し、炎症が軽快して、一見、正常に見える状態でもしばらく外用を続ける治療だ。
図3 アトピー性皮膚炎の外用療法
おわりに
最後に「かゆみ」の研究について述べる。アトピー性皮膚炎患者にとってはそのような皮膚の損傷は痒みの悪化につながる。自然科学研究機構生理学研究所の望月秀紀特任教授は、男女18人に蚊に刺された腕の写真を見せる実験をして、痒みを感じて「掻きたい」欲求を発する脳内の仕組みを確認した。
そのときの脳の活動を、磁気共鳴断層画像装置(fMRI)を使って調べた結果、中脳や線条体(掻きたいという欲求)といった報酬系と呼ばれる脳部位が強く反応することを、世界で初めて明らかにした(図4)。
具体的な信号のやりとりはわからないが、このつながりを弱めれば悪循環のアトピー性皮膚炎で掻くのを『止める』治療につながるかもしれない。
図4 痒いところを掻いて快感が生じているときに
報酬系と呼ばれる脳部位(中脳や線条体)が活動
参考文献
1) https://sirabee.com/2016/04/27/114351/(2019年8月5日アクセス)
2) https://allergy72.jp/anaphylaxis/allergy.html(2019年8月5日アクセス)
3) https://www.seikyoonline.com/article/9264EA64B88263C99E5B74387A19187B(2019年8月5日アクセス)
4) http://www.nips.ac.jp/contents/release/entry/2014/01/post-262.html(2019年8月5日アクセス)

島田邦男
琉球ボーテ(株) 代表取締役
1955年東京生まれ 工学博士 大分大学大学院工学研究科卒業、化粧品会社勤務を経て日油㈱を2014年退職。 日本化粧品技術者会東京支部常議員、日本油化学会関東支部副支部長、日中化粧品国際交流協会専門家委員、東京農業大学客員教授。 日油筑波研究所でグループリーダーとしてリン脂質ポリマーの評価研究を実施。 日本油化学会エディター賞受賞。経済産業省 特許出願技術動向調査委員を歴任。 主な著書に 「Nanotechnology for Producing Novel Cosmetics in Japan」((株)シーエムシー出版) 「Formulas,Ingredients and Production of Cosmetics」(Springer-Veriag GmbH) 他多数
ライブラリ・無料
ダウンロードコーナー

PDF版 ダウンロード販売
気になる刊行物をPDFで
ダウンロード
紙面を探す

化粧品
マーケティング情報
マーケティングに役立つ
情報が満載
紙面を探す

調査レポート
化粧品業界での戦略に
役立つレポート
レポートを探す

粧界データ集
メーカー製品一覧などの
データ集をダウンロード
無料でダウンロード

化粧品容器カタログ
ライブラリー
容器メーカーの
最新カタログを公開中
カタログを探す

デジタル紙面版
2010年1月から最新号まで
デジタルアーカイブ化
無料で見る
刊行物紹介

週刊/毎週月曜日発行
週刊粧業
化粧品、日用品、医薬品、美容業、装粧品、エステティック等を中心とした生産・流通産業界の総合専門情報紙。

季刊/年4回
C&T
化粧品、日用品、アクセサリーなどの業界別の市場動向をはじめ、戦略、流通、経営、マーケティングを扱う情報専門誌。
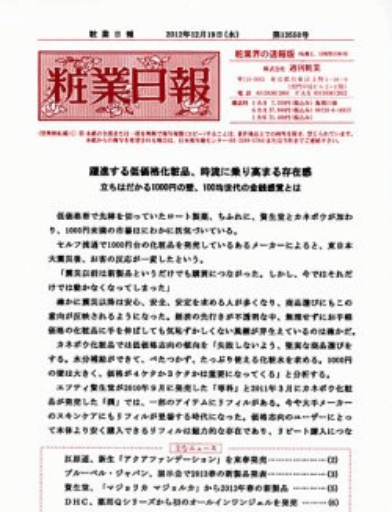
週刊/毎週月曜日発行
粧業日報
化粧品、トイレタリー、石鹸、歯磨、日用品に関する情報の速報版。業界のエグゼクティブ必読の情報紙。
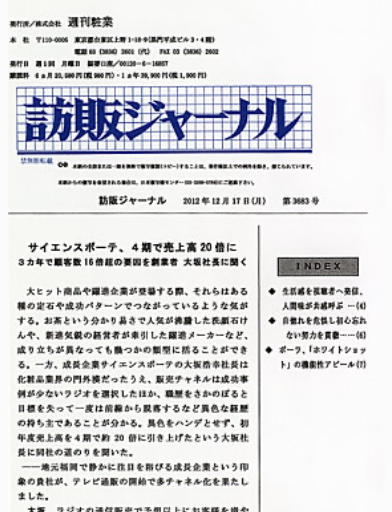
週刊/毎週月曜日発行
訪販ジャーナル
昭和33年に創刊された、わが国初の訪問販売化粧品業界の専門情報紙。
速報ニュース
アクセスランキング
- 日間
- 週間
- 月間