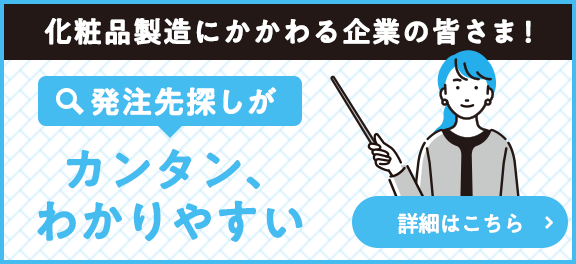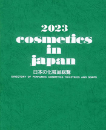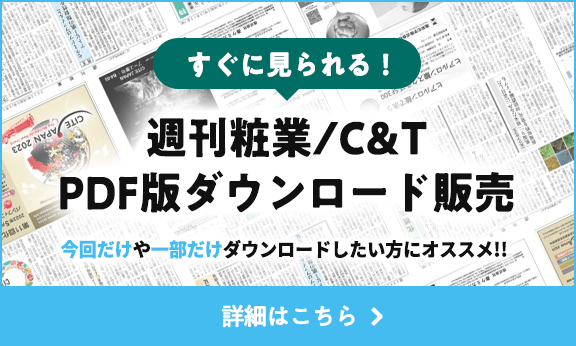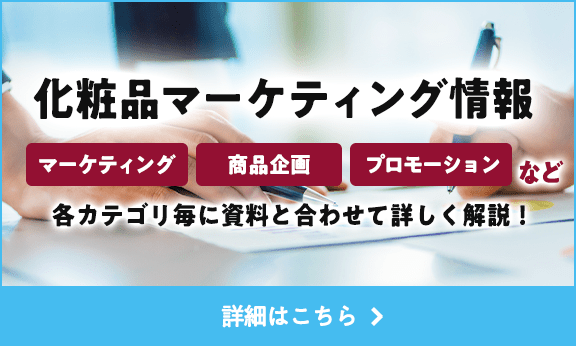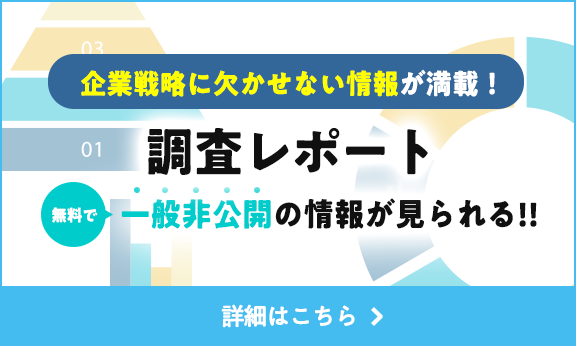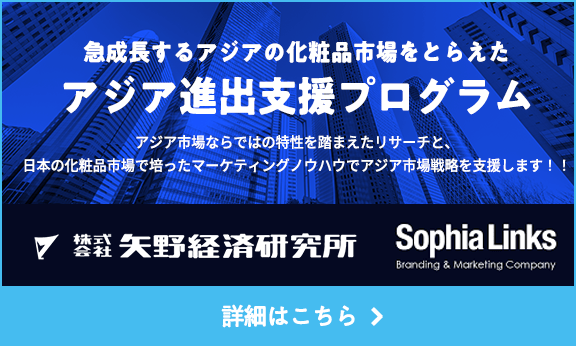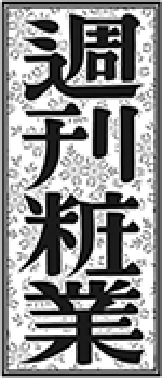第28回 コケではなく苔
【C&T2016年10月号10面にて掲載】
はじめに
美容家の佐伯チズ女史の座右の銘に、「子供を叱るな、来た道じゃ。年寄り怒るな、行く道じゃ」がある。子供の姿はかつての自分であり、お年寄りは自分の将来の姿を見せてくれている、ということらしい。
しかし、70代でもピンピンコロリを目指して、日夜努力を重ねてはいるもののいずれは介護を受ける日がくるかもしれない。年齢がわからない見た目を目指す美魔女や、お母さんに見えない容貌を競い合わなくても、女性ならいくつになっても“若い子だけが可愛いいわけじゃないのよ!”ってメッセージを発したい。
オリンピックで聞いた「君が代は…苔のむすまで」の国歌に、“苔”が歌われているのは日本だけだ。苔のむすまでという言葉は「苔が生えるほどの長い時間」という意味が込められている。苔のむすまで長い時間を過ごしてきた普通の女性をコケにしない、高齢化について今回は述べてみる。
超高齢社会1、2)
65歳以上の人が総人口に占める割合のことを"高齢化率"という。この高齢化率が7%を超えると「高齢化社会」、14%を超えると「高齢社会」、21%を超えると「超高齢社会」ということになる。日本は1970年に高齢化率が7%を超え、1994年には14%を超えている。2010年には戦後生まれの65歳が登場し、2015年10月1日の時点での高齢者人口は過去最高の2924万人で、高齢化率は23.0%と初めて21%を突破し、日本は超高齢社会に突入した(図1)。
この推計によれば、高齢者人口は今後も2020年まで急速に増え続ける。その後はやや安定するが、総人口が減少していくため高齢化率はさらに上昇し続けて、2035年には33.4%に達すると見込まれている。日本人の3人に1人が65歳以上という"超超高齢社会"になるわけである。
65歳以上の高齢者を「高齢者は身体機能や認知機能が低下する」、といった既成概念で括ることは適切ではなく、個々人によって状況は異なっている。また、高齢者の社会参加意識についても、「働けるうちはいつまでも働きたい」と考える高齢者が30%を超える(60歳以上の有職者)という調査結果もある。
高齢者全体が増えていくことで、生産年齢人口の減少、社会保障費や介護負担が増えていくだろうが、元気な高齢者も増えていくはずだ。個人差はあるものの、2030年時点では約8割の高齢者は、介護不要で自立的に暮らしているという予測データがある(図2)。
図2 要介護者の推移の割合
65歳といっても平均寿命からみれば、まだ15年から20年くらいの人生がある。セカンドライフを積極的に楽しもうという志向がより顕著になっていくはずだ。
世界一の長寿国である日本が先進各国と比べて豊かな超高齢社会を実現するためには、介護老人を減らすことよりもまず、高齢者の健康を増進するというアンチエイジングの考え方を普及させていく必要がありそうだ。
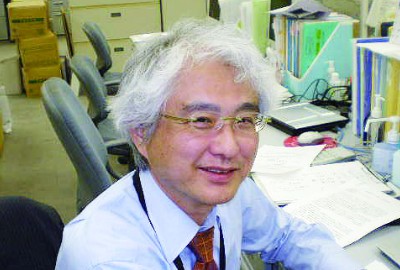
島田邦男
琉球ボーテ(株) 代表取締役
1955年東京生まれ 工学博士 大分大学大学院工学研究科卒業、化粧品会社勤務を経て日油㈱を2014年退職。 日本化粧品技術者会東京支部常議員、日本油化学会関東支部副支部長、日中化粧品国際交流協会専門家委員、東京農業大学客員教授。 日油筑波研究所でグループリーダーとしてリン脂質ポリマーの評価研究を実施。 日本油化学会エディター賞受賞。経済産業省 特許出願技術動向調査委員を歴任。 主な著書に 「Nanotechnology for Producing Novel Cosmetics in Japan」((株)シーエムシー出版) 「Formulas,Ingredients and Production of Cosmetics」(Springer-Veriag GmbH) 他多数
ライブラリ・無料
ダウンロードコーナー

PDF版 ダウンロード販売
気になる刊行物をPDFで
ダウンロード
紙面を探す

化粧品
マーケティング情報
マーケティングに役立つ
情報が満載
紙面を探す

調査レポート
化粧品業界での戦略に
役立つレポート
レポートを探す

粧界データ集
メーカー製品一覧などの
データ集をダウンロード
無料でダウンロード

化粧品容器カタログ
ライブラリー
容器メーカーの
最新カタログを公開中
カタログを探す

デジタル紙面版
2010年1月から最新号まで
デジタルアーカイブ化
無料で見る
刊行物紹介

週刊/毎週月曜日発行
週刊粧業
化粧品、日用品、医薬品、美容業、装粧品、エステティック等を中心とした生産・流通産業界の総合専門情報紙。

季刊/年4回
C&T
化粧品、日用品、アクセサリーなどの業界別の市場動向をはじめ、戦略、流通、経営、マーケティングを扱う情報専門誌。
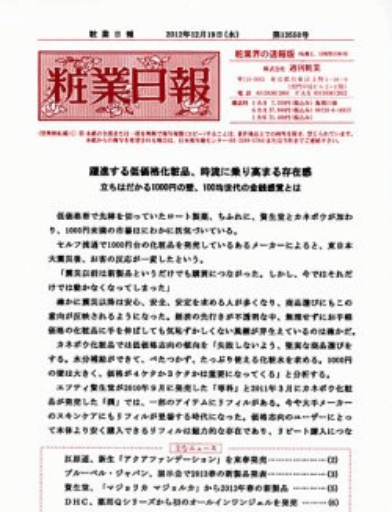
週刊/毎週月曜日発行
粧業日報
化粧品、トイレタリー、石鹸、歯磨、日用品に関する情報の速報版。業界のエグゼクティブ必読の情報紙。
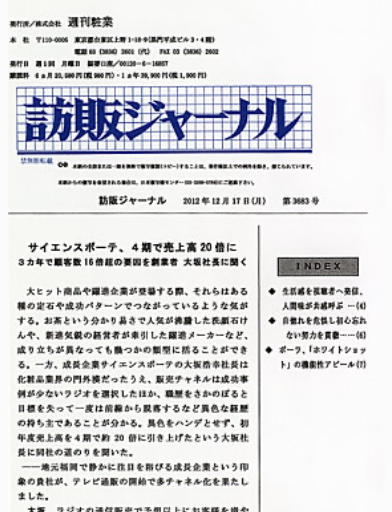
週刊/毎週月曜日発行
訪販ジャーナル
昭和33年に創刊された、わが国初の訪問販売化粧品業界の専門情報紙。
速報ニュース
アクセスランキング
- 日間
- 週間
- 月間